
《日本での水墨画の広がり》
唐から絵画の技術が伝わる最初は、人物画における【著色(着色)】
山水画では麻布に墨のみにで描く【麻布山水】もあるが、主流は群青、緑青などの色による【緑青山水】
この【緑青山水】が【やまと絵】になっていく。
▶︎漢字が文字文化の始まりであったが、やはり奈良時代あたりから【万葉仮名】という日本固有の文字文化が展開してゆく
連綿体という文字をつなげる形態が生まれ「高野切」はその典型
▶︎【墨絵】は【著色(着色)】の下絵として描かれたともされるが【白描絵巻(はくびょうえまき)】として展開していく。
仏画の図様を墨で描いた【白描図像】や「鳥獣戯画」など。
▶︎【墨絵】が大きく変化するのは鎌倉時代にかけて、禅宗の来朝僧らとともに水墨画法が入ってくる。
ゆえに「茶」等と同様、「禅」と結びつけられての展開となる。

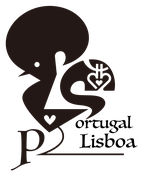
コメントをお書きください